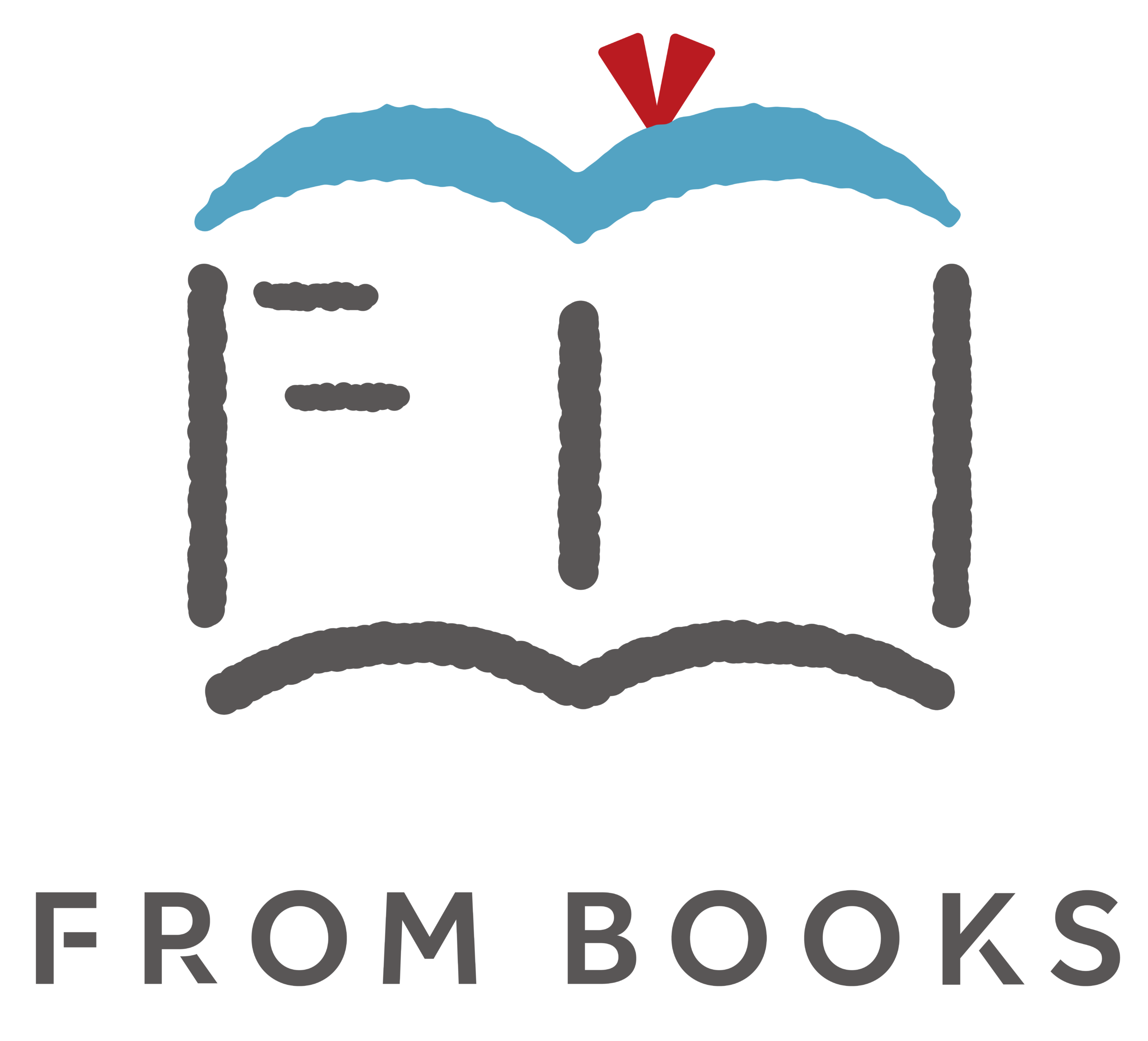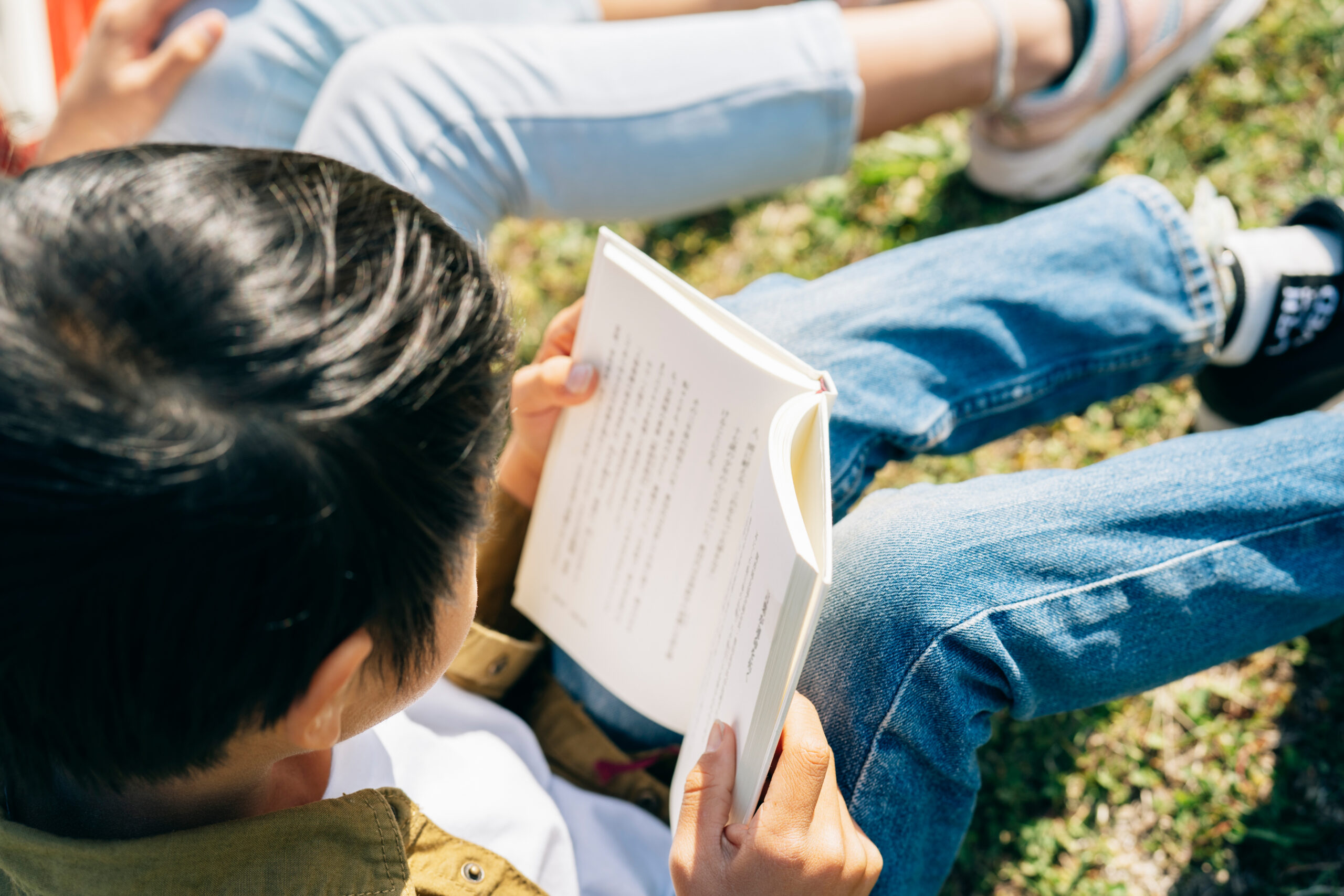【子育てパパママ必見】寝る前の読書が快眠と自己投資になるって本当?コスパ最強の夜習慣を徹底解説!

「毎日、育児と仕事に追われてクタクタ…」「やっと子どもが寝たと思ったら、自分の時間なんてあっという間…」そう感じている子育て世代のパパママ、たくさんいらっしゃるのではないでしょうか?
「寝る前に本を読んでも、かえって目が冴えて眠れなくなることはないの?」そんな風に不安に思っている方もいるかもしれませんね。でも実は、寝る前の読書は、あなたの睡眠の質を高め、日々の疲れを癒し、さらには将来のための自己投資にもなる、まさに「コスパ最強」の夜習慣なんです!
この記事では、寝る前の読書がなぜ快眠に繋がるのか、そしてどのようにすれば効果的に読書を取り入れられるのかを、子育て世代の皆さんの悩みに寄り添いながら、分かりやすく解説していきます。読み終わる頃には、きっと心も体も満たされ、心地よい眠りに包まれることでしょう。
さあ、私たちと一緒に、今日から充実した夜の読書習慣を始めてみませんか?
寝る前の読書が快眠に導く理由
読書は、安眠を促す効果が期待できます。 例えば静かなソファなどで本を読むことで、心身ともにリラックスした状態へと導かれ、良質な睡眠へとつながる可能性があります。 読書という行為は、自分だけの特別な時間となり、心の平穏をもたらします。 その結果、自律神経のバランスが整い、「副交感神経」が優位になることで、入眠しやすくなり、深い眠りへとつながると言われています。
読書に費やす時間、無駄だと思っていませんか?実は快眠と自己投資の宝庫!
毎日忙しいパパママにとって、「読書の時間なんてない!」と感じるかもしれません。でも、ちょっと待ってください!寝る前の読書は、単なる趣味ではなく、あなたの心と体の健康、そして未来への投資になるんです。
1. 読書がもたらす極上のリラックス効果:なぜ眠りやすくなるの?
「本を読むことで眠くなる」と感じたことはありませんか?それは、読書があなたの心身をリラックス状態へと導いてくれるからです。
自律神経のバランスを整え、副交感神経を優位に
読書は、あなただけの静かで特別な時間。この「自分だけの時間」が、心の平穏をもたらし、乱れがちな自律神経のバランスを整えてくれます。
私たちの体は、「活動と興奮を司る交感神経」と「休息と鎮静をもたらす副交感神経」という2つの自律神経によって、生命維持に必要な機能がコントロールされています。日中の活動モードである交感神経が優位な状態から、リラックスモードの副交感神経が優位な状態へとスムーズに切り替わることが、質の良い睡眠には不可欠なんです。
実は、興奮系の交感神経から休息系の副交感神経への切り替えには、約5分かかると言われています。それに対して、副交感神経から交感神経への切り替えはわずか約0.2秒と非常に速いんです。つまり、寝る前にゆったりとした時間を持つことが、スムーズな入眠を促すカギになります。読書はまさに、その「ゆったりとした時間」を作るのに最適な方法と言えるでしょう。
2. 寝る前の読書は「最も効率的な自己投資」!記憶力UPの秘密
「寝る前に読書をする時間があるなら、もっと違うことに使いたい…」と感じる方もいるかもしれません。しかし、寝る前の読書は、実は非常に効率的な自己投資なんです。
記憶の定着を促す「睡眠学習効果」
読書によって得た知識は、寝ている間に整理され、記憶として定着しやすくなることが知られています。これは「睡眠学習効果」とも呼ばれる現象です。例えば、英単語の暗記や、日中に学んだビジネス知識など、寝る前の読書でインプットした情報は、より効果的に記憶に残りやすくなります。
読書が脳にもたらすメリットとして、文字からイメージする過程で想像力や共感力が鍛えられたり、脳細胞のつながりが強化されて記憶力などが向上したりすることが挙げられます³。
読書と年収の相関性:未来の自分への投資
「読書量が年収に影響するの?」と疑問に思うかもしれません。結論から言うと、読書量と年収には相関関係があるという調査結果が複数あります。例えば、2021年のマイナビの調査では、年収1,500万円以上の層で月に3冊以上読書する割合が30.8%と、他の年収層と比べて最も高い数値を示しています。
ただし、読書量が多いからといって必ず年収が上がるという直接的な因果関係は、現在のところ明確なデータで示されているわけではありません。しかし、読書量が多い人ほど、以下のような理由で年収が高くなる可能性があると考えられています⁵。
- 知識やスキルの獲得: 専門書やビジネス書を読むことで、仕事に直結する新しい知識やスキルを得ることができます。
- 思考力や創造性の向上: さまざまな情報に触れることで、物事を多角的に捉え、新しいアイデアを生み出す力が養われます。
- 自己投資の姿勢: 読書習慣があること自体が、自身の成長に対する積極的な姿勢を示していると言えるでしょう。
【ちょっと計算してみましょう】
もしあなたが毎日20分、寝る前に読書をするとします。1年間で約121.6時間(20分/日 × 365日 = 7300分 = 121.6時間)を読書に費やすことになります。これは、週に約2時間半程度の勉強時間とほぼ同じです。この時間で、年間で10冊以上のビジネス書を読むことも十分に可能です。
一般的な新刊ビジネス書の価格を1冊1,800円と仮定します。もしあなたが年間12冊(月1冊)ビジネス書を読むとすると、年間で21,600円の投資です。この知識があなたのスキルアップに繋がり、年間所得が1万円でも上がったとしたら、2年と少しで十分に元が取れてしまう計算になります。もちろん、知識の習得やスキルアップは、年収アップだけでなく、仕事の満足度向上やストレス軽減にも繋がります。読書は、まさに将来の自分への先行投資なのです。
※上記の計算は一般的な書籍価格と年収に関する調査に基づく試算であり、効果を保証するものではありません。
寝る前の読書、ココが落とし穴!「眠れない」を避ける3つの秘訣
「寝る前に読書をしたら、かえって目が冴えて眠れなくなった…」そんな経験はありませんか?実は、寝る前の読書は、やり方を間違えると逆効果になってしまうこともあるんです。
目の酷使による緊張や疲労、強い光を浴びること、物語に没頭しすぎてしまうことなどが、睡眠を妨げる原因になることがあります。
でも大丈夫!これからご紹介する3つのポイントを押さえれば、あなたはもう失敗しません。快眠のための読書術を身につけて、心地よい眠りを手に入れましょう。
秘訣1:場所と照明が鍵!「寝室以外」で「明るすぎない」光を
どこで、どんな光の中で読むか。これが快眠読書の第一歩です。
快眠のための読書場所:「寝室以外」がベスト
「ベッドや布団で本を開くのが一番落ち着く」と感じる方も多いですよね。しかし、布団は脳が「休息の場所」と認識しているため、そこで読書をすると、脳が「ここは活動する場所だ」と混乱してしまい、睡眠の質に影響が出る可能性があります⁷。
深い眠りを妨げないためには、寝る前の読書は寝室以外の場所で行うのが賢明です。リビングのソファや、書斎の椅子など、リラックスできる別の場所で読書を終えてから寝室に向かいましょう。これにより、布団は純粋な睡眠空間として脳に認識され、スムーズな入眠を促すことができます。
眠りの質を高める照明:「暖色系の間接照明」が理想
就寝前の部屋の明るさは、およそ「50ルクス以下」が推奨されています。これは、月明かりがおよそ0.5~1.0ルクスであることを考えると、かなり暗い状態です。一方で、読書をする際の適切な明るさは、500ルクスが適切だとされています。
つまり、寝室全体の照明は暗くしつつ、手元や周囲をデスクライトなどでピンポイントに明るくするのがおすすめです。特に注目したいのは「色温度」です。青白い光は脳を覚醒させてしまうため、リラックス効果のあるオレンジ色の暖色系の光を選びましょう。明るさを調節できる調光機能付きの照明器具なら、その日の気分や疲れ具合に合わせて調整できるので、より快適な読書空間を作り出せますね。
秘訣2:読書時間は短めに!「20分以内」と「休憩」が大切
集中して本を読んでいると、あっという間に時間が過ぎてしまいますよね。でも、寝る前の読書は、短時間で切り上げるのが快眠のコツです。
短時間集中が鍵:読書は「20分以内」が目安
目の前のものを見つめる時間が長くなると、目の周囲の筋肉が活動し、緊張状態になります。また、同じ体勢を長時間続けることも、体のあちこちに緊張を及ぼします。この緊張が高まると、残念ながら「交感神経」が優位になり、「副交感神経」の働きが抑制されてしまうんです。これでは、せっかくの読書が眠りを妨げる原因になりかねません。
入眠をスムーズにするためには、5~20分程度を目安に一度休憩を挟むと良いでしょう。タイマー機能などを活用して、時間を決めて読書に取り組むのがおすすめです。
読書中の姿勢にも注意!
寝そべって読むのは気持ちが良いですが、首や肩に負担がかかり、体も緊張してしまいます。できるだけ、椅子に座って背筋を伸ばし、リラックスできる姿勢で読むように心がけましょう。
秘訣3:良質な睡眠へ導く本の選び方:「紙媒体」で「心を落ち着かせる」内容を
どんな本を選ぶかも、快眠読書にとっては非常に重要なポイントです。
電子書籍より「紙媒体」を選ぼう
手軽さが魅力の電子書籍ですが、就寝前の読書には注意が必要です。スマートフォンやタブレットなどのデバイスから発せられる「強い光(ブルーライト)」は、私たちの生体リズムを司る「睡眠ホルモン・メラトニン」の生成を妨げてしまう可能性があります¹⁰。メラトニンが十分に分泌されないと、眠りが浅くなり、質の良い睡眠が得られません。
活字が印刷された紙媒体の書籍は、光の影響を受けずに安心して読書に集中できます。活字本を選ぶ際は、目の負担にならないよう、文字の大きさに着目し、読みやすさを重視すると良いでしょう。
内容は「心を落ち着かせる」ものを選ぶ
スリリングなミステリーや、感情が揺さぶられるような内容は、寝る前の読書には不向きです。興奮して脳が活発になり、かえって眠れなくなってしまう可能性があります。
以下のようなジャンルの本がおすすめです。
- 心温まるエッセイや短編集: 優しい気持ちになれる物語や、共感できるエッセイは、心を穏やかにしてくれます。
- 風景描写が美しい小説: 情景をゆっくりと想像することで、心が落ち着き、リラックスできます。
- 教養を深める新書や実用書: 興味のある分野の知識を、ゆったりとしたペースで吸収することで、知的好奇心を満たしつつ、穏やかな気持ちになれます。ただし、刺激が強すぎないものを選びましょう。
- 詩集: 短い言葉の中に深い意味が込められた詩は、思考を巡らせながらも、心を静かに落ち着かせることができます。
静かな環境で、心地よい物語の世界に浸ることで、自然と眠りの準備が整います。
子育てパパママの読書時間を確保する秘策
「分かってはいるけど、寝る前の数分すら確保するのが難しい!」そう感じる方もいるかもしれませんね。実際に、日本の小学生から高校生の子どもを持つ家庭を対象とした調査では、約半数の子どもが平日に読書をしないと回答しており、読書時間の減少傾向が見られます¹¹。親自身も、まとまった時間を確保するのが難しいのが現状でしょう。
そんな子育て世代のパパママでも、読書時間を確保するためのちょっとした秘策をご紹介します。
秘策1:タイムボックスで「読書時間」を確保する
毎日決まった時間に「この時間は読書をする!」と決めて、他の予定を入れないようにしましょう。例えば、「子どもが寝た後の21時から21時20分は読書タイム」と決めるなど、短時間でも良いので習慣化することが大切です。無理なく続けられるよう、最初は5分でも10分でもOKです。
秘策2:家族と協力して「お互いの時間」を作る
夫婦で協力し合って、お互いに読書や趣味の時間を確保できるよう、子どもの就寝後の家事分担を見直すのも良いでしょう。例えば、今日はパパが食器洗いをして、ママが読書。明日はママが洗濯物を畳んで、パパが読書、というように交代制にするのも一案です。お互いの「自分時間」を尊重し合うことで、家族みんながハッピーになれます。
秘策3:読書会や読書コミュニティに参加してみる
オンラインやオフラインで、読書会や読書コミュニティに参加してみるのもおすすめです。読書仲間がいることでモチベーションを維持できますし、新しい本との出会いもあります。子育て世代向けの読書会に参加すれば、同じ悩みを抱える仲間と情報交換もできて、心強いかもしれません。
まとめ:寝る前の読書で、今日から快眠と自己成長を掴み取ろう!
良質な睡眠は、心身の健康を維持するために不可欠です。そして、寝る前の読書は、あなたの自律神経を整え、快眠を促す効果があるだけでなく、将来の自分への投資にもなる素晴らしい習慣です。
この記事でご紹介した「3つの秘訣」を実践することで、あなたは今日からでも質の高い睡眠を得ることが可能です。
- 場所と照明: 寝室以外で、暖色系の明るすぎない照明(手元は適切に照らす)の下で読書を。
- 時間と休憩: 20分以内を目安に、適度な休憩を挟んで。
- 本の種類: 電子書籍ではなく紙媒体を。心を落ち着かせる内容を選んで。
子育て中の忙しい毎日でも、少しの工夫で読書の時間を確保し、その効果を最大限に引き出すことができます。寝る前の読書を通じて、心も体も満たされる安らぎの時間を手に入れ、知識やスキルを磨き、あなた自身の未来を切り開いていきましょう!
さあ、今日から寝る前の読書習慣を始めて、心地よい眠りに包まれ、健やかな毎日を手に入れましょう!